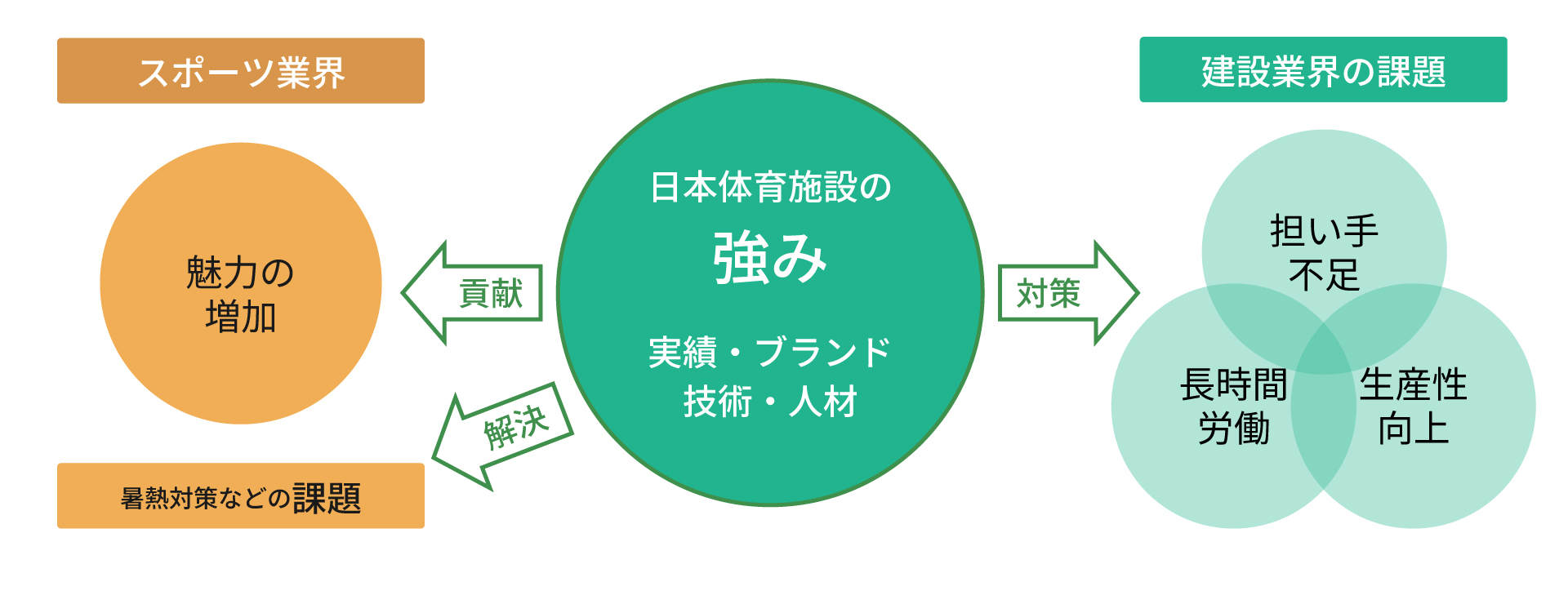冬の芝生管理とは?サッカーやラグビー場の芝生一年中グリーンな理由
-日本体育施設の専門技術者が教えます!-
-日本体育施設の専門技術者が教えます!-
日本体育施設の技術者が、様々な疑問に答えるシリーズ。今回は「冬のスタジアムの芝生が青々しいのはなぜ?」。
回答するのは日本体育施設で芝生管理技術者として長年携わる芝生先生です。

回答するのは日本体育施設で芝生管理技術者として長年携わる芝生先生です。

みなさん、こんにちは! 芝生管理技術者の芝生先生です。
寒い冬にサッカーやラグビーの試合を見に行くと、「どうして芝生がこんなに鮮やかなグリーンなんだろう?」と驚かれたことはありませんか?逆に学校、近所の公園、自宅の庭の芝生は茶色くて枯れてしまっている?と思われることも多いかもしれません。
この記事では、冬でもグリーンの芝生には、どんな秘密があるのか?その謎を解説してゆきたいと思います。
冬でも芝生が青々としている…実はその秘密は「芝生の種類」と管理方法にあるのです。
寒い冬にサッカーやラグビーの試合を見に行くと、「どうして芝生がこんなに鮮やかなグリーンなんだろう?」と驚かれたことはありませんか?逆に学校、近所の公園、自宅の庭の芝生は茶色くて枯れてしまっている?と思われることも多いかもしれません。
この記事では、冬でもグリーンの芝生には、どんな秘密があるのか?その謎を解説してゆきたいと思います。
冬でも芝生が青々としている…実はその秘密は「芝生の種類」と管理方法にあるのです。
冬も青々とした芝生の秘密
Q.1冬なのにスタジアムの芝生が青々と生い茂っているのはなぜ?
A.1
スタジアムの芝生の秘密は、暖かい季節に強い芝と、寒さに強い芝の2種類を組み合わせて育てているからです。
サッカーやラグビー場に使われている天然芝には大きく「暖地型芝生」と「寒地型芝生」の2種類があります。
スタジアムの芝生の秘密は、暖かい季節に強い芝と、寒さに強い芝の2種類を組み合わせて育てているからです。
サッカーやラグビー場に使われている天然芝には大きく「暖地型芝生」と「寒地型芝生」の2種類があります。
冬なのにサッカーやラグビー場の芝生が青々としているのは、これら2種類の芝生をうまく組み合わせて使用しているのです。
ただ、スタジアムが寒冷地にある場合、「寒地型芝生」のみを使用していることもあります。

Q.2育ち方が違う「暖地型芝生」と「寒地型芝生」とは?
A.2
では、その2種類の芝には、どのような違いがあるのでしょう?
「暖地型芝生」とは、簡単に言うと暖かい時期によく育つ芝生のことを指します。主に夏の時期、気温でいうと25℃~35℃くらいの時期に青々とし、良く育ちます。
しかし、寒さには弱く、冬の時期は休眠し茶色く変色してしまいます。よく冬の公園やグラウンドで見られる茶色く変色した芝生は暖地型芝生の仲間です。
一方で「寒地型芝生」は、涼しい時期によく育つ芝生のことを指します。主に春や秋の時期、気温でいうと15℃~25℃の時期によく育つことが特徴です。
寒さに強く、冬の時期でも茶色く変色せずに緑色を保つことが可能です。反対に暑さには弱く、変色することはありませんが夏の生育は繊細なため、維持管理は非常に難しい種類です。
では、その2種類の芝には、どのような違いがあるのでしょう?
「暖地型芝生」とは、簡単に言うと暖かい時期によく育つ芝生のことを指します。主に夏の時期、気温でいうと25℃~35℃くらいの時期に青々とし、良く育ちます。
しかし、寒さには弱く、冬の時期は休眠し茶色く変色してしまいます。よく冬の公園やグラウンドで見られる茶色く変色した芝生は暖地型芝生の仲間です。
一方で「寒地型芝生」は、涼しい時期によく育つ芝生のことを指します。主に春や秋の時期、気温でいうと15℃~25℃の時期によく育つことが特徴です。
寒さに強く、冬の時期でも茶色く変色せずに緑色を保つことが可能です。反対に暑さには弱く、変色することはありませんが夏の生育は繊細なため、維持管理は非常に難しい種類です。
Column 01

暖地(だんち)型芝生の種類と特徴
暖地型芝生にも様々な種類がありますが、ここでは国内でよく使われる芝生として大きく「日本芝類」と「西洋芝(バミューダグラス)類」を紹介します。
日本芝とは、日本に自生している芝生で「ノシバ」と「コウライシバ」があります。それぞれ公園や道路の法面などに使われることが多いです。日本の気候に合っており管理や手入れが楽です。
一方、西洋芝とは海外から輸入された芝生の総称で、その中にバミューダグラスという種類があります。主に日本のサッカー場などのスポーツ施設に使われているのは、このバミューダグラスの仲間である「ティフトン419」という品種です。
一方、西洋芝とは海外から輸入された芝生の総称で、その中にバミューダグラスという種類があります。主に日本のサッカー場などのスポーツ施設に使われているのは、このバミューダグラスの仲間である「ティフトン419」という品種です。

この品種はアメリカ原産で、日本芝と比べて生育のスピードや回復力に優れていることが特徴です。スポーツ施設によく採用される理由も、スポーツ利用による傷を早く回復できるためです。
Column 02

寒地(かんち)型芝生の種類と特徴
寒地型芝生にも様々な種類がありますが、その全てが西洋芝で主にヨーロッパ原産です。日本国内のスポーツ施設で主に使われている寒地型芝生は「ペレニアルライグラス、ケンタッキーブルーグラス、トールフェスク」の3種類があります。
それぞれ同じ寒地型芝生ですが微妙に違いがあり、例えばペレニアルライグラスは、生育スピードは3種類の中で一番早いですが、夏の暑さには特に弱いです。
その他にも葉のきめ細かさや耐久性などにもそれぞれ違いがあります。
その他にも葉のきめ細かさや耐久性などにもそれぞれ違いがあります。

寒地型芝生は管理が非常に難しいですが、うまく管理できた時には非常に美しいピッチに仕上がります。サッカー場などには使われませんが、ゴルフ場に使われている「ベント芝」も寒地型芝生の仲間です。
Q.3夏も冬も1年中緑色に生い茂る芝生を維持する方法とは?
A.3
寒地型芝生のみを採用すれば1年中グリーンに生い茂った芝生を維持することができますが、先に触れたように、夏が暑い地域では管理が難しく、涼しい地域での採用が現実的です。
ただ、最初にお話しした通り、冬には茶色く変色してしまいます。
そこで、暖地型芝生を採用したグラウンドでは「ウィンターオーバーシード(ウインターオーバーシーディング)」という管理方法で一年中グリーンを維持しています。
Q.4ウィンターオーバーシード(ウインターオーバーシーディング)とは?
A.4
ウィンターオーバーシード(ウインターオーバーシーディング)とは、寒い時期に暖地型芝生が休眠し色が茶色く変色する前に、寒地型芝生の種をまいて育てることで一年中グリーンを保つ技術です。
芝生の種類を暖地型から寒地型(またはその逆)へと切り替えることを専門用語で「トランジション」といい、暑い時期は暖地型芝生を、寒い時期は寒地型芝生を育てることになります。
暖地型芝生を採用しているJリーグの試合会場のほとんどで、この技術が取り入れられています。
永続的な考え方で言ったら苗植えから育成する手法や、小判での張り芝工法に尽きると思います。
新設工事の時には、専門機械を使った機械撒き芝工法が用いられます。
ウィンターオーバーシード(ウインターオーバーシーディング)とは、寒い時期に暖地型芝生が休眠し色が茶色く変色する前に、寒地型芝生の種をまいて育てることで一年中グリーンを保つ技術です。
芝生の種類を暖地型から寒地型(またはその逆)へと切り替えることを専門用語で「トランジション」といい、暑い時期は暖地型芝生を、寒い時期は寒地型芝生を育てることになります。
暖地型芝生を採用しているJリーグの試合会場のほとんどで、この技術が取り入れられています。
永続的な考え方で言ったら苗植えから育成する手法や、小判での張り芝工法に尽きると思います。
新設工事の時には、専門機械を使った機械撒き芝工法が用いられます。
[関連記事 ウィンターオーバーシード〜冬でもグリーンの芝生を保つ秘密〜]
Q.5寒地型芝のみ使用する場合があると聞きました。なぜ?
A.5
寒地型芝生のみを使用しているグラウンドは少ないですが日本にもあります。
例えば浦和レッズのホームでもあり、東京オリンピックの会場にもなった「埼玉スタジアム」、ヴィッセル神戸のホームである「ノエビアスタジアム神戸」、当社が長年に渡って管理してきた、ベガルタ仙台のホームである「ユアテックスタジアム仙台」などがあります。(※2025年5月時点)??
その他、2023年に建設された北海道日本ハムファイターズの本拠地「エスコンフィールドHOKKAIDO」にも寒地型芝生が採用されました。
暖地型と寒地型の混合「ウインターオーバーシード」がポピュラーですが、プロ・ アスリートが利用するスタジアムでは、年間を通じてプレイ環境の均一性を重視します。繊細な技を競い合う選手にとって「冬は冬芝、夏は夏芝」という性質の違う芝生が混ざり合う、切り替わりの時期が一番不安です。そのリスクを避けるため、寒地型芝一本で通年運用する選択をする施設もあるのです。
寒地型芝生のみを使用しているグラウンドは少ないですが日本にもあります。
例えば浦和レッズのホームでもあり、東京オリンピックの会場にもなった「埼玉スタジアム」、ヴィッセル神戸のホームである「ノエビアスタジアム神戸」、当社が長年に渡って管理してきた、ベガルタ仙台のホームである「ユアテックスタジアム仙台」などがあります。(※2025年5月時点)??
その他、2023年に建設された北海道日本ハムファイターズの本拠地「エスコンフィールドHOKKAIDO」にも寒地型芝生が採用されました。
暖地型と寒地型の混合「ウインターオーバーシード」がポピュラーですが、プロ・ アスリートが利用するスタジアムでは、年間を通じてプレイ環境の均一性を重視します。繊細な技を競い合う選手にとって「冬は冬芝、夏は夏芝」という性質の違う芝生が混ざり合う、切り替わりの時期が一番不安です。そのリスクを避けるため、寒地型芝一本で通年運用する選択をする施設もあるのです。
ただし、近年は地球温暖化の影響で寒地型芝生を管理することがより一層難しくなってきたため、寒地型芝生のグラウンドは減少傾向です。

Q.6ハイブリッド芝の使用もあると聞きました。どんなものですか?
A.6
ここでいうハイブリッド芝というのは、天然芝をベースに一定割合の人工芝や人工繊維を混ぜた芝のことを指します。
天然芝に人工芝や人工繊維を混ぜることで、芝生の根が絡みつき、天然芝の強度を補うことが可能となります。
日本国内では、先ほど紹介した「ノエビアスタジアム神戸」や当社が施工した、大分トリニータのホームである「クラサスドーム大分」などが、ハイブリッド芝を採用している珍しいスタジアムです。
ここでいうハイブリッド芝というのは、天然芝をベースに一定割合の人工芝や人工繊維を混ぜた芝のことを指します。
天然芝に人工芝や人工繊維を混ぜることで、芝生の根が絡みつき、天然芝の強度を補うことが可能となります。
日本国内では、先ほど紹介した「ノエビアスタジアム神戸」や当社が施工した、大分トリニータのホームである「クラサスドーム大分」などが、ハイブリッド芝を採用している珍しいスタジアムです。
Q.7着色剤の使用をしている場合もあるのですか?
A.7
天然芝を管理するにあたって、美しい緑を保つために着色剤というものを使い、色付けすることがあります。
寒い時期に、暖地型芝生が休眠して色が落ちる前に使います。
色付けの他に、熱の吸収効率を高めて地温の保温する効果や、冬の寒さから保護する効果、春先の芽吹きを早める効果も期待できます。
天然芝を管理するにあたって、美しい緑を保つために着色剤というものを使い、色付けすることがあります。
寒い時期に、暖地型芝生が休眠して色が落ちる前に使います。
色付けの他に、熱の吸収効率を高めて地温の保温する効果や、冬の寒さから保護する効果、春先の芽吹きを早める効果も期待できます。

安全性は人体に害がない原料を使用しているので、正しく使えば問題ありません。
※もちろんこの着色剤を直接飲んだりはできません。
※もちろんこの着色剤を直接飲んだりはできません。
Q.8冬ならではの芝生の管理方法はありますか?
A.8
冬の芝生管理 というのは、実は案外やることはほとんどありません。というのも冬の時期は寒すぎて、何をしても芝生が動かないからです。
冬は芝生を休め、春に向けてエネルギーをためる時期になります。
冬の芝生管理 というのは、実は案外やることはほとんどありません。というのも冬の時期は寒すぎて、何をしても芝生が動かないからです。
冬は芝生を休め、春に向けてエネルギーをためる時期になります。

それでは冬の時期に何をしているのかというと、寒風から芝生を守り少しでも表面温度をあげるために養生シートと呼ばれるビニルシートを芝生に被せたり、グローライトと呼ばれる補光装置を使って冬の少ない日照を補い光合成を促したりと、とにかく芝生を保護することを行っていきます。
[関連記事 芝生の冬枯れを防ぐ!芝生管理のプロが教える冬季(12月~2月)の芝生管理]