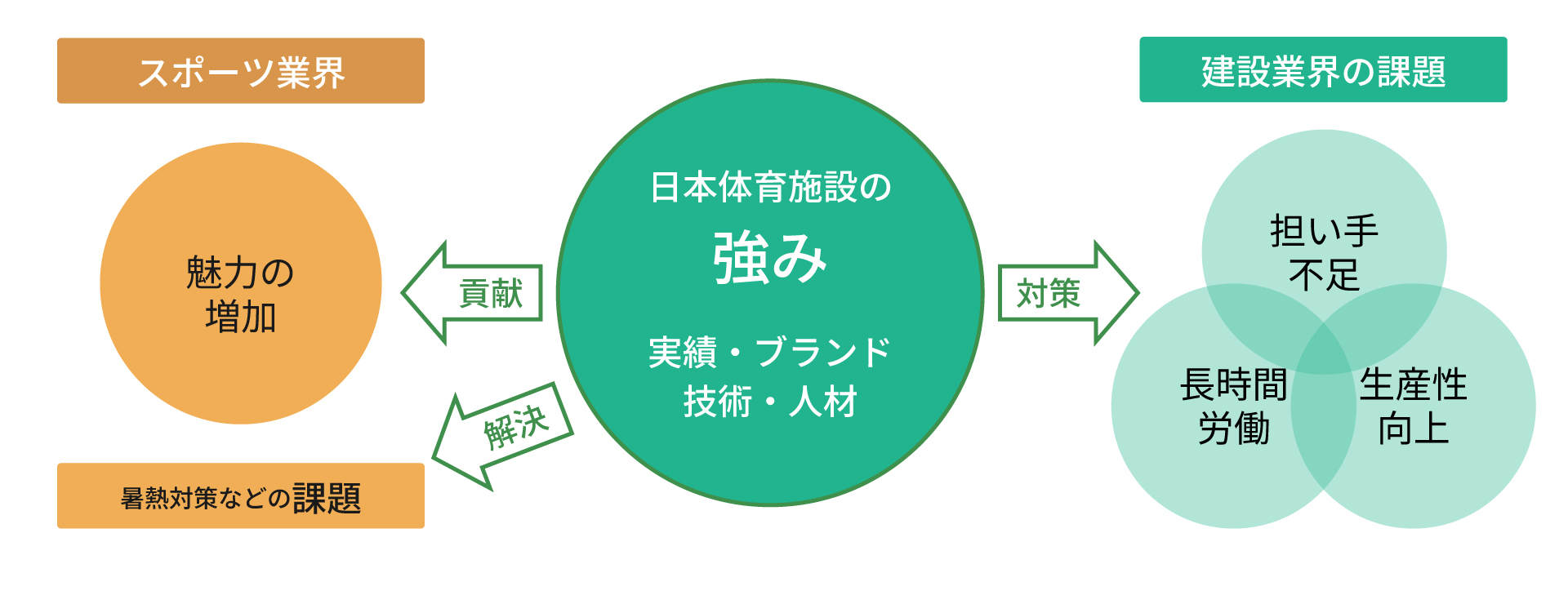ウィンターオーバーシード〜冬でも青々とした芝生を保つ秘密〜
-日本体育施設の専門技術者が教えます!-
-日本体育施設の専門技術者が教えます!-
日本体育施設の技術者が、様々な疑問に答えるシリーズ。今回は「ウインターオーバーシード」について。
回答するのは日本体育施設で芝生管理技術者として長年携わる芝生先生です。

回答するのは日本体育施設で芝生管理技術者として長年携わる芝生先生です。

みなさん、こんにちは! 芝生管理技術者の芝生先生です。
「ウィンターオーバーシード(ウィンターオーバーシーディング)」とは、夏芝が休眠する前に冬芝をまき、季節の切り替わりをスムーズにする技術です。
スタジアムの冬芝管理では欠かせない方法で、見た目の美しさだけでなく、プレイ環境の安全性にもつながります。
「ウィンターオーバーシード(ウィンターオーバーシーディング)」とは、夏芝が休眠する前に冬芝をまき、季節の切り替わりをスムーズにする技術です。
スタジアムの冬芝管理では欠かせない方法で、見た目の美しさだけでなく、プレイ環境の安全性にもつながります。
冬も青々とした芝生の秘密
Q.1ウィンターオーバーシードが必要な理由は?
A.1
もともとは冬でも美しい芝生でプレイできるようにしたい、冬でも美しい芝生で集客をしたいという思いからウィンターオーバーシードの技術が考案されました。
もともとは冬でも美しい芝生でプレイできるようにしたい、冬でも美しい芝生で集客をしたいという思いからウィンターオーバーシードの技術が考案されました。

ウィンターオーバーシードをせずに、退色した暖地型芝生の上でプレイをすることは
・損傷が回復しない
・ダメージが蓄積し春先の芽出しが遅れる
・雑草が混入しやすくなり景観が損なわれる
・ダメージが蓄積し春先の芽出しが遅れる
・雑草が混入しやすくなり景観が損なわれる
などの問題があります。これら問題を解決するためにもウィンターオーバーシードという技術は非常に有効です。
Q.2ウィンターオーバーシードの実施時期は?
A.2
ウィンターオーバーシードを行う時期は「夏芝が休眠する直前の秋」に実施します。地域によって多少前後するでしょうが、概ね9月~10月の時期に行います。気温が下がりすぎる前に播種(はしゅ)するのがポイントです。
この時期の気候は、暖地型芝生の生育ピークが過ぎ、寒地型芝生の生育に適した条件になりつつあるためです。
ウィンターオーバーシードを行う時期は「夏芝が休眠する直前の秋」に実施します。地域によって多少前後するでしょうが、概ね9月~10月の時期に行います。気温が下がりすぎる前に播種(はしゅ)するのがポイントです。
この時期の気候は、暖地型芝生の生育ピークが過ぎ、寒地型芝生の生育に適した条件になりつつあるためです。

Q.3ウィンターオーバーシードの方法は?
A.3
ウインターオーバーシードは、季節に沿って実施します。
秋〜 冬を迎える前に仕込みを開始
秋に夏芝を短く刈り、土壌を整えてから寒地型芝生の種を蒔きます。
種を蒔くときは、地面に種が接するように暖地型芝生の隙間にしっかり種を落として、乾燥させないことが重要です。
種を蒔くときは、地面に種が接するように暖地型芝生の隙間にしっかり種を落として、乾燥させないことが重要です。

冬〜 発芽した芝生を守り育てる
秋から冬にかけて発芽した寒地型芝生をしっかり育てます。冬芝が芽吹いたら、低温や踏圧に耐えられるよう、適度に養生します。施肥や刈込を繰り返し程よい芽数とハリのある葉っぱに仕上げることを目指します。
こうした作業を順調に行うには、スタジアム等では試合スケジュールとの兼ね合いも大きな課題です。
こうした作業を順調に行うには、スタジアム等では試合スケジュールとの兼ね合いも大きな課題です。
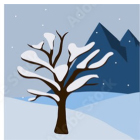
春〜 入れ替わりのタイミング
育った寒地型芝生を衰退させ、暖地型芝生に切り替えていく時期です。
刈高を落としたり、更新作業を繰り返したりしてとにかく寒地型芝生に少しずつストレスを与えていきます。
刈高を落としたり、更新作業を繰り返したりしてとにかく寒地型芝生に少しずつストレスを与えていきます。

夏〜 夏芝に完全移行
完全に寒地型芝生を消失させることを目標にします。
関東以南であれば暑さで自然に消えていきますが、そうでない場合継続して更新作業や低刈りにてストレスを与えていきます。
関東以南であれば暑さで自然に消えていきますが、そうでない場合継続して更新作業や低刈りにてストレスを与えていきます。

Q.4ウィンターオーバーシードは家庭の庭でもできるの?
A.4
理論上できなくはないですが、難易度はかなり高いです。
その理由の一つに、家庭用の芝生の品種は「ノシバ」か「コウライシバ」を使うことが多いですが、これら品種はウィンターオーバーシードには向いていません。なぜなら、これら品種は一般的にサッカー場に採用されているティフトン芝よりも生育が遅いからです。
理論上できなくはないですが、難易度はかなり高いです。
その理由の一つに、家庭用の芝生の品種は「ノシバ」か「コウライシバ」を使うことが多いですが、これら品種はウィンターオーバーシードには向いていません。なぜなら、これら品種は一般的にサッカー場に採用されているティフトン芝よりも生育が遅いからです。

そのため、春から夏の時期に寒地型芝生から暖地型芝生へ切り替える際に、上手に切り替えることが難しいです。温度や芝生の状態を見ながら慎重に時期を見定めるシビアな作業なため、ある程度基礎知識や技術がないと難しいかもしれません。
ですが、もちろん挑戦してみること自体は良いことだと思います。
ですが、もちろん挑戦してみること自体は良いことだと思います。
Q.5芝生の手入れってこんな性格の人が向いている!?
A.5
難しい質問ですね。
私が思うに「細かいところに気が付く」性格の人でしょうか。
芝生を管理していくにあたって、芝生の細かい表情の変化にどこまで気が付けるかが上手に管理するコツな気がします。
難しい質問ですね。
私が思うに「細かいところに気が付く」性格の人でしょうか。
芝生を管理していくにあたって、芝生の細かい表情の変化にどこまで気が付けるかが上手に管理するコツな気がします。

ただ、神経質になりすぎて必要以上に水や肥料を与えるのもかえって害になるので、時には慌てず堂々としておくことも必要です。
何はともあれ、非常に奥が深い仕事でもあるので、ひたむきに芝生と向き合うことが重要だと日々感じております。