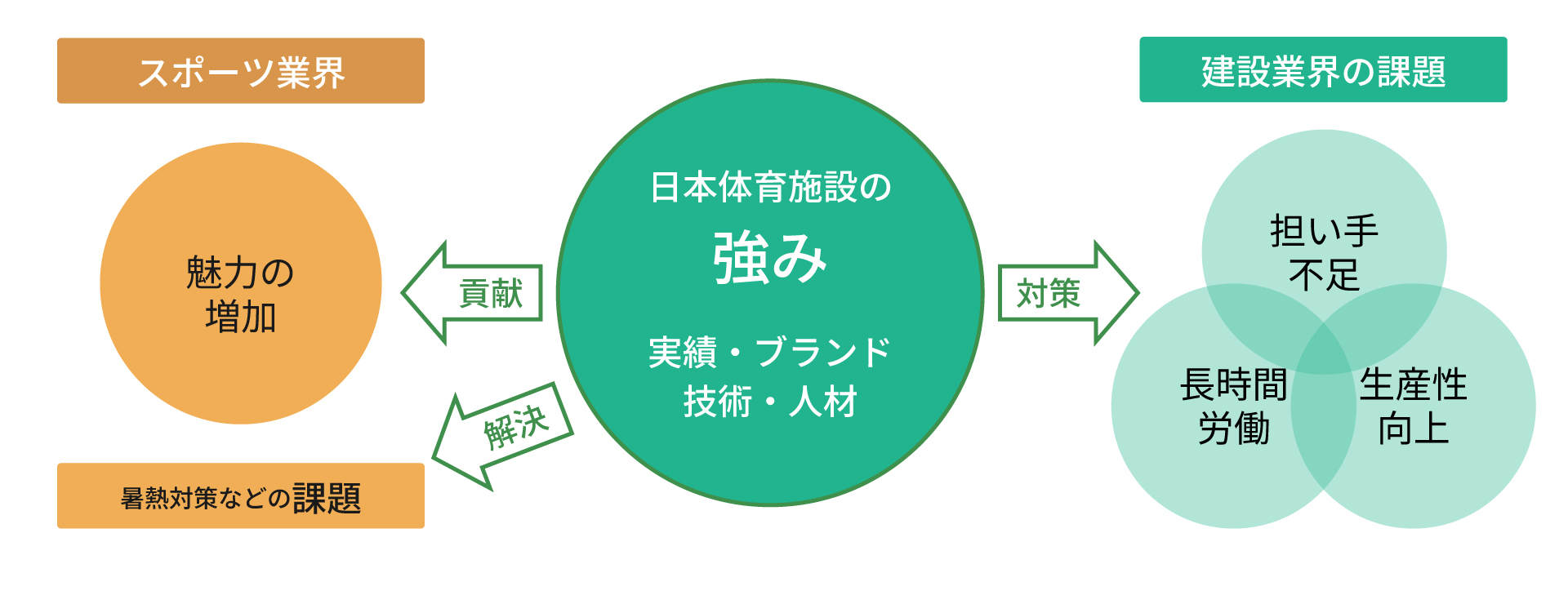芝生の冬枯れを防ぐ?! 〜芝生管理のプロが教える冬季(12月~2月)の芝生管理〜
-日本体育施設の専門技術者が教えます!-
-日本体育施設の専門技術者が教えます!-
日本体育施設の技術者が、様々な疑問に答えるシリーズ。今回は「ウインターオーバーシード」について。回答するのは日本体育施設で芝生管理技術者として長年携わる芝生先生です。


みなさん、こんにちは! 芝生管理技術者の芝生先生です。
みなさんのお庭でも「冬になると芝が茶色くなる」と悩んでいませんか?
日本芝(高麗芝など)は冬に休眠するため、どうしても枯れたように見えてしまいます。ただし、施肥・目土入れ・刈高調整で根を守れば、春に元気に芽吹いてくれます。
では、家庭で行う冬の芝生管理はどう言ったものが考えられるでしょう。
みなさんのお庭でも「冬になると芝が茶色くなる」と悩んでいませんか?
日本芝(高麗芝など)は冬に休眠するため、どうしても枯れたように見えてしまいます。ただし、施肥・目土入れ・刈高調整で根を守れば、春に元気に芽吹いてくれます。
では、家庭で行う冬の芝生管理はどう言ったものが考えられるでしょう。
芝生の冬枯れを防ぐ方法はあるの?
Q.1芝生の冬枯れを防ぐ方法はあるの?
A.1
結論から言うと、2025年現在の技術でも日本における芝生の冬枯れ(休眠)を防ぐ方法はありません。
冬枯れをさせないためには温度が肝です。プロのスタジアムでも地温コントロールシステムなどで温めますが、それでも休眠します。
結論から言うと、2025年現在の技術でも日本における芝生の冬枯れ(休眠)を防ぐ方法はありません。
冬枯れをさせないためには温度が肝です。プロのスタジアムでも地温コントロールシステムなどで温めますが、それでも休眠します。
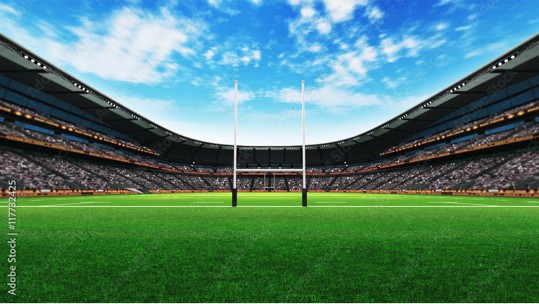
「それでもどうにかして冬枯れさせたくない!」といった場合は、ビニールハウス温室などでガンガンに温めればできそうですが、電気代もかなりかかります。
冬でも芝生が緑に見えているのは、ウィンターオーバーシードによって寒地型芝生を植えているからなんです。
家庭でもウィンターオーバーシーディングを行えば冬枯れを防ぐことも、理論上は可能です。ただ、細かな管理が必要なため、相応な技術と経験がなければ難しく、現実的ではないかもしれません。
スタジアムなどで青々とした冬の芝生を目にすると、ご家庭でも!という気持ちは十分理解できますが、冬ならではの芝生の表情を楽しむ、といった考え方もあるのではないでしょうか?
冬でも芝生が緑に見えているのは、ウィンターオーバーシードによって寒地型芝生を植えているからなんです。
家庭でもウィンターオーバーシーディングを行えば冬枯れを防ぐことも、理論上は可能です。ただ、細かな管理が必要なため、相応な技術と経験がなければ難しく、現実的ではないかもしれません。
スタジアムなどで青々とした冬の芝生を目にすると、ご家庭でも!という気持ちは十分理解できますが、冬ならではの芝生の表情を楽しむ、といった考え方もあるのではないでしょうか?
Q.2冬の芝生管理、初心者がやりがちな失敗とは?
A.2
初心者が やりがちな失敗として考えられるのは、冬の時期にやたらと管理に手をかけることです。
冬の芝生は寒さで色が茶色になるのであって、痛んだり枯れたりしているのではありません。さらには病気だと勘違いする場合もあるかもしれませんが、寒さで色落ちすることは、芝生の正しい生理現象です。
初心者が やりがちな失敗として考えられるのは、冬の時期にやたらと管理に手をかけることです。
冬の芝生は寒さで色が茶色になるのであって、痛んだり枯れたりしているのではありません。さらには病気だと勘違いする場合もあるかもしれませんが、寒さで色落ちすることは、芝生の正しい生理現象です。

慌てて過剰に施肥をしたり、薬をまいても効果はありません。「そういうものだ」とどっしり構えることを心がけましょう。
Q.3家庭での冬の芝生管理、場所に合わせたプロならではの方法はありますか?
A.3
プロといえど、寒い時期は芝生が休眠してしまうので管理作業はほとんどないのが実情です。
それはご家庭の庭でも、公園でも、スタジアムでも同じです。
ご家庭での冬の管理作業なら、たまに散水(月に1~2回)、雑草抜き、軽めのサッチングなどをやると良いかと思われます。
プロといえど、寒い時期は芝生が休眠してしまうので管理作業はほとんどないのが実情です。
それはご家庭の庭でも、公園でも、スタジアムでも同じです。
ご家庭での冬の管理作業なら、たまに散水(月に1~2回)、雑草抜き、軽めのサッチングなどをやると良いかと思われます。
サッチングというのは、刈込で発生した刈草や古く枯れた芝の葉や茎などが堆積したものを「サッチ」というのですが、これが溜まりすぎると悪影響なのでこれを取り除く作業です。
家庭のお庭ですと、ガーデン芝生レーキ(熊手状、または先が鍬状になったトンボのようなもの)などで軽く表面をかいてあげるといいと思います。
あまり激しくやるとかえって痛めるのでほどほどにやるのがコツです。
家庭のお庭ですと、ガーデン芝生レーキ(熊手状、または先が鍬状になったトンボのようなもの)などで軽く表面をかいてあげるといいと思います。
あまり激しくやるとかえって痛めるのでほどほどにやるのがコツです。

Q.4春に向けて!2月下旬から行う芝生の管理作業は?
A.4
繰り返しになりますが、冬の時期は、重めの更新作業をしないのが原則です。
※芝生の更新作業:芝生の春の新しい生育シーズンに向けて、芝生と土壌の環境を整える一連の作業
しかし3月上旬以降の春の芽出しを少しでも早めるために、軽めの更新作業を行い、芝生に刺激を与える場合はあります。
エアレーション(穴あけ)やサッチ除去をして、芝の呼吸を助けることも重要です。
その場合、少し暖かい日に、本当に軽いスパイキングやバーチカルにて刺激を与えます。時期も地域によりますが、行うとしても3月頭くらいでしょうか。
この時期の更新作業を強めにやると芝生に大ダメージを与えてしまうので慎重に判断したほうがいいと思います。
繰り返しになりますが、冬の時期は、重めの更新作業をしないのが原則です。
※芝生の更新作業:芝生の春の新しい生育シーズンに向けて、芝生と土壌の環境を整える一連の作業
しかし3月上旬以降の春の芽出しを少しでも早めるために、軽めの更新作業を行い、芝生に刺激を与える場合はあります。
エアレーション(穴あけ)やサッチ除去をして、芝の呼吸を助けることも重要です。
その場合、少し暖かい日に、本当に軽いスパイキングやバーチカルにて刺激を与えます。時期も地域によりますが、行うとしても3月頭くらいでしょうか。
この時期の更新作業を強めにやると芝生に大ダメージを与えてしまうので慎重に判断したほうがいいと思います。
Column 01

エアレーションとは?
固くなりすぎるなど、芝生の生育に適さなくなった土壌を改善する方法の一つです。
▼期待できる効果
①土壌に空気(酸素)を供給
②水はけをよくする
③根の新陳代謝を促進し、病気やトラブルを予防
①土壌に空気(酸素)を供給
②水はけをよくする
③根の新陳代謝を促進し、病気やトラブルを予防

具体的には土壌に穴を開ることで、空気や水を行き渡らせることを促進します。柔らかく水と空気の含まれた土壌は、芝生の根の生育にとても役立ちます。
また、水はけが良くなる効果もあり、地面に水溜りができにくくなることで、通気性や排水性がより改善されます。このことで、地中の微生物も活性化し、養分も増え、病原菌の抑制も期待できます。
作業には、スパイク状の道具を使う「スパイキング」、固くなった土をパイプ状に掘り出してくれる「ローンパンチ」などを使用します。
また、水はけが良くなる効果もあり、地面に水溜りができにくくなることで、通気性や排水性がより改善されます。このことで、地中の微生物も活性化し、養分も増え、病原菌の抑制も期待できます。
作業には、スパイク状の道具を使う「スパイキング」、固くなった土をパイプ状に掘り出してくれる「ローンパンチ」などを使用します。
Q.5プロの現場① スタジアムの冬の芝生管理とは?
A.4
Jリーグの試合会場となるようなスタジアムではJリーグシーズンの都合上2月にも試合があります。本来この時期は、養生にあてたい期間ですが仕方ありません。
そこでこのようなJリーグ会場では、冬はシート養生で保温したり、グローライトで光合成を促進したり、会場によっては「地温コントロールシステム」によって土壌から温めることで芝生の生育を促す、または劣化を抑制します。
Jリーグの試合会場となるようなスタジアムではJリーグシーズンの都合上2月にも試合があります。本来この時期は、養生にあてたい期間ですが仕方ありません。
そこでこのようなJリーグ会場では、冬はシート養生で保温したり、グローライトで光合成を促進したり、会場によっては「地温コントロールシステム」によって土壌から温めることで芝生の生育を促す、または劣化を抑制します。

その他、緑の着色剤を散布し、美観性をあげることもあります。
[関連記事 芝生の冬枯れを防ぐ?! 芝生管理のプロが教える冬季(12月~2月)の芝生管理]
[関連記事 ウィンターオーバーシード〜冬でも緑色の芝生を保つ秘密〜]
Q.6プロの現場② 公園の冬の芝生管理
A.5
公園の芝生というのは、サッカースタジアムと違って常緑であることが求められているわけではありません。公園では「常緑を目指さない」ケースがほとんどです。
冬は茶色の芝生で自然な景観を残します。木々が秋冬の表情を見せる中で、芝生のみ青々としているのは、自然の情景を求める公園には、そぐわないと思います。
公園の芝生というのは、サッカースタジアムと違って常緑であることが求められているわけではありません。公園では「常緑を目指さない」ケースがほとんどです。
冬は茶色の芝生で自然な景観を残します。木々が秋冬の表情を見せる中で、芝生のみ青々としているのは、自然の情景を求める公園には、そぐわないと思います。

もちろん、美観を伴う作業は重要なので、芝生周りの清掃や雑草抜きは行います。
芝生自体に冬の時期にあれこれ手をかけるのは、かえって芝生をダメにするので、無理はしません。
秋冬らしい自然な表情の色を保たせつつ、雑草駆除などの整備に留め、掃除を行きとどかせておくことが、公園の冬の芝生管理では重要だと考えます。
芝生自体に冬の時期にあれこれ手をかけるのは、かえって芝生をダメにするので、無理はしません。
秋冬らしい自然な表情の色を保たせつつ、雑草駆除などの整備に留め、掃除を行きとどかせておくことが、公園の冬の芝生管理では重要だと考えます。