スポーツ公園の管理・運営の基礎知識
ー日本体育施設の公園管理運営士が教えます!
ー日本体育施設の公園管理運営士が教えます!
このページではスポーツ公園の管理運営の基礎知識をご紹介します。回答するのは、公園管理運営士である日本体育施設パークマネージメント事業部の山崎さん。
INDEX
- スポーツ施設と都市公園について
- Q.1都市公園・スポーツ施設にはどんなものがありますか?種類を教えてください
- Q.2スポーツ施設と都市公園は増えていっているの?
- 「指定管理者制度」について
- Q.3「指定管理者制度」とは?公共スポーツ施設の管理を民間企業が行う理由
- Q.4「指定管理者制度」と都市公園管理運営の「業務委託」の違いは何ですか?
- Q.5指定管理者制度とPFI法の違いは何ですか?
- スポーツ公園の管理運営業務について
- Q.6公園の管理運営業務とは、どんなことをするもの?
- Q.7スポーツ公園では、どんなことがサービス向上につながりますか?
- 公園や公共スポーツ施設の施設・安全管理・環境保全について
- Q.8公園の安全管理はどんなことに取り組んでいますか?
- Q.9公園の環境保全はどんなことに取り組んでいますか?
- 公園や公共スポーツ施設の地域連携について
- Q.10地域連携として行っていることは?
スポーツ施設と都市公園について
まずは、スポーツ施設と都市公園に関わる言葉の定義を公園管理運営士である山崎さんが解説します。
Q.1都市公園・スポーツ施設にはどんなものがありますか?種類を教えてください
A.1
国土交通省が示す都市公園の種類の中で、スポーツ施設に関連する公園は「運動公園」が一番大きなくくりです。「総合運動公園」や「運動場」という公園の名称を耳にしますが、運動公園の中に含まれています。
「総合運動公園」は、みんなが公園で楽しく、安全に公園で過ごせるように作られた都市公園法で「都市公園に設ける運動施設の割合は、敷地面積の50%を超えてはならない」とされています。運動公園の割合が50%以上の公園が「運動場」と位置づけられています。
他にも「スタジアム」や「アリーナ」、「スポーツ・コンプレックス」や「ボールパーク」などスポーツ施設を取り巻く様々な名称があります。
国土交通省が示す都市公園の種類の中で、スポーツ施設に関連する公園は「運動公園」が一番大きなくくりです。「総合運動公園」や「運動場」という公園の名称を耳にしますが、運動公園の中に含まれています。
「総合運動公園」は、みんなが公園で楽しく、安全に公園で過ごせるように作られた都市公園法で「都市公園に設ける運動施設の割合は、敷地面積の50%を超えてはならない」とされています。運動公園の割合が50%以上の公園が「運動場」と位置づけられています。
都市公園の種類(国土交通省都市局公園緑地・景観課)
他にも「スタジアム」や「アリーナ」、「スポーツ・コンプレックス」や「ボールパーク」などスポーツ施設を取り巻く様々な名称があります。
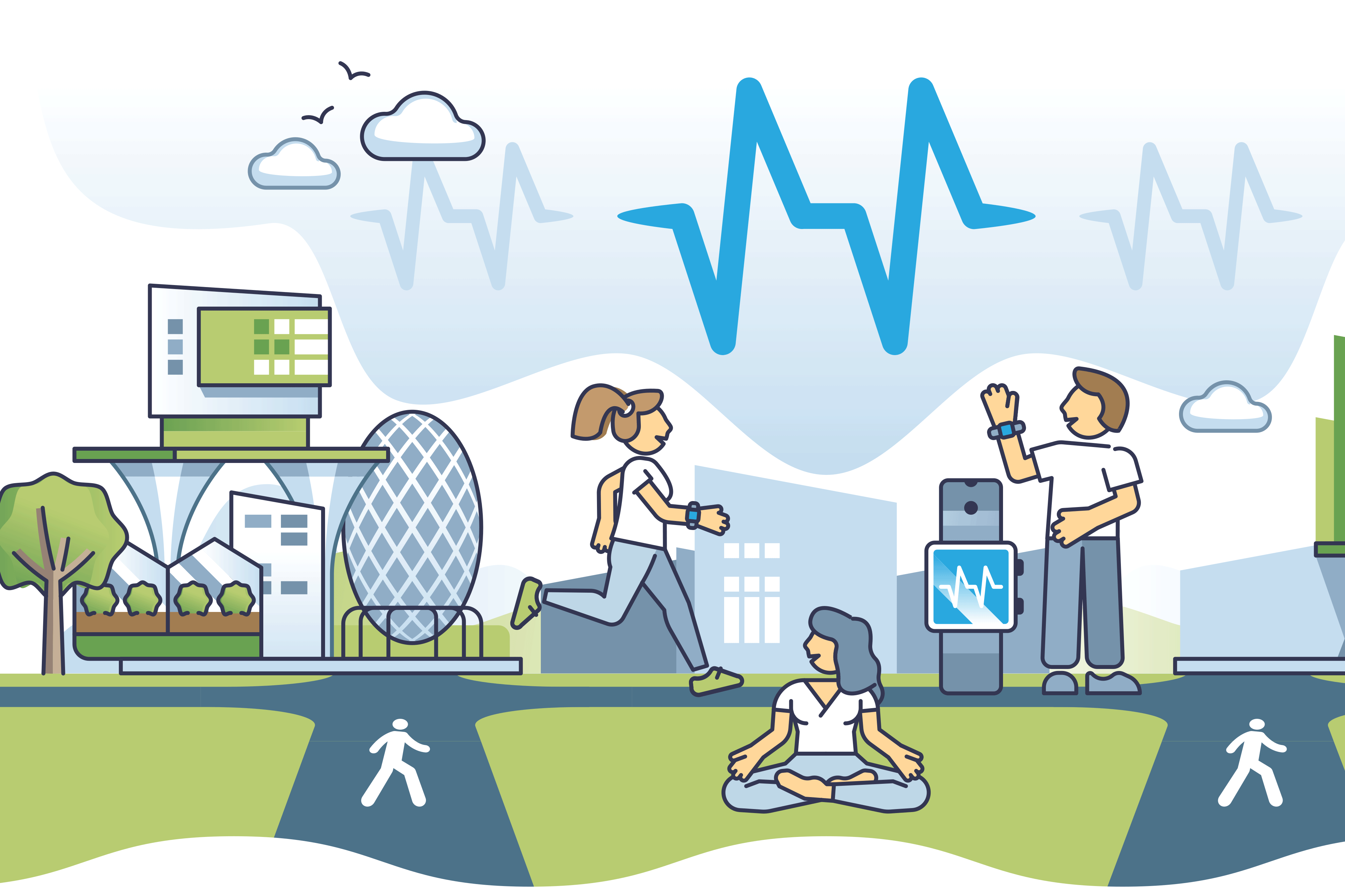
さらに、スポーツ施設には、学校の運動場や体育館も含まれ、公立学校の屋外運動場の開放し地域スポーツの場を拡充する動きが進んでいます。

Q.2スポーツ施設と都市公園は増えていっているの?
A.2
以下の通り、国民一人当たりの都市公園等面積は増加しています。
一方で、スポーツ施設を含むレクリエーション施設は、2000年代から公共施設の老朽化を受けて本格化したストック適正化の影響により減少傾向となっています。特に少子化や人口減少の影響で廃校が進んでいます。こうした廃校になった施設のリノベーションや再活用の事例も出てきており、地域づくりの新しい取り組みに注目が集まっています。
以下の通り、国民一人当たりの都市公園等面積は増加しています。
令和4年度末都市公園等整備の状況
令和4年度末の全国の都市公園等の整備量(ストック)は、令和3年度末と比較し、
・箇所数は、113,828箇所から114,707箇所と、879箇所増加
・面積は、約130,084haから約130,531haと、約447ha増加
・一人当たり都市公園等面積は、約10.8㎡/人
令和3年度のスポーツ庁の統計では、公共スポーツ施設は51,740箇所もあり、当社が関わる施設管理の領域は、まだまだ広く感じます。
その中でも、スポーツ庁が推進するスタジアム・アリーナ 構想や、PFIなど事業手法なども注目されていますが、スポーツ施設に求められる役割はこれまで以上に多岐にわたっています。
「指定管理者制度」について
Q.3「指定管理者制度」とは?公共スポーツ施設の管理を民間企業が行う理由
A.3
2003年の地方自治法の改正に伴い、民間企業が公共の施設の管理が出来るようになりました。民間事業者の持つノウハウを生かし、住民サービスの向上と経費の削減等を図ることを目的にしています。これを「指定管理者制度」と呼びます。
それまでスポーツ施設を含む公共または公共的団体の管理運営は、政令で定められた出資法人等に委託先が限定されていました。ただ、住民はじめ利用者のニーズが多様化してきたことから、より効果的、効率的に対応するためには民間のノウハウの活用が有効であると判断されました。
「民間でできることは民間で」の流れもあり、「公民連携」で多様なニーズに答えようと、管理の受託主体の法律上の制限がなくなり、民間企業が管理できるようになったのです。
2003年の地方自治法の改正に伴い、民間企業が公共の施設の管理が出来るようになりました。民間事業者の持つノウハウを生かし、住民サービスの向上と経費の削減等を図ることを目的にしています。これを「指定管理者制度」と呼びます。
それまでスポーツ施設を含む公共または公共的団体の管理運営は、政令で定められた出資法人等に委託先が限定されていました。ただ、住民はじめ利用者のニーズが多様化してきたことから、より効果的、効率的に対応するためには民間のノウハウの活用が有効であると判断されました。
「民間でできることは民間で」の流れもあり、「公民連携」で多様なニーズに答えようと、管理の受託主体の法律上の制限がなくなり、民間企業が管理できるようになったのです。
Q.4「指定管理者制度」と都市公園管理運営の「業務委託」の違いは何ですか?
A.4
「指定管理者制度」では、利用料金を自らの収入として収受することが可能で、サービスの向上による利用者増、自主事業の工夫により収入を増やすこともできます。これを「利用料金制度」といいます。
「指定管理者制度」を採用した自治体は、管理権限の行使はしませんが、設置者としての責任を果たすため、必要に応じて指示等を行うことになります。自治体に集まる地域住民のニーズや要望をもとに、すり合わせを行いながら主体的に公共施設を運営していくことが求められます。
一方、業務委託の場合、一般的に公共施設の管理運営は設置者である自治体が主体で行います。そのため民間企業等は「業務委託」を結び、その契約の範囲内で自治体の仕様通りに管理することが求められます。この場合、公共施設の管理やイベント等の施策を行う際に制限が多く、予算も決められているため柔軟な運用ができにくいと言えます。
都市公園の「業務委託」では、自治体との契約の範囲内で自治体の仕様通りに管理することが求められます。一方、「指定管理者制度」では、民間の活力やノウハウを活かした管理運営が求められます。発案企画から実現までを一貫して民間が行えるところが業務委託との大きな違いかと思います。
当社では、指定管理者として、中野区や町田市など、委託管理としては、品川区の中央公園・海上公園他と荒川区立宮前公園を行っています。
「指定管理者制度」では、利用料金を自らの収入として収受することが可能で、サービスの向上による利用者増、自主事業の工夫により収入を増やすこともできます。これを「利用料金制度」といいます。
「指定管理者制度」を採用した自治体は、管理権限の行使はしませんが、設置者としての責任を果たすため、必要に応じて指示等を行うことになります。自治体に集まる地域住民のニーズや要望をもとに、すり合わせを行いながら主体的に公共施設を運営していくことが求められます。
一方、業務委託の場合、一般的に公共施設の管理運営は設置者である自治体が主体で行います。そのため民間企業等は「業務委託」を結び、その契約の範囲内で自治体の仕様通りに管理することが求められます。この場合、公共施設の管理やイベント等の施策を行う際に制限が多く、予算も決められているため柔軟な運用ができにくいと言えます。
都市公園の「業務委託」では、自治体との契約の範囲内で自治体の仕様通りに管理することが求められます。一方、「指定管理者制度」では、民間の活力やノウハウを活かした管理運営が求められます。発案企画から実現までを一貫して民間が行えるところが業務委託との大きな違いかと思います。
当社では、指定管理者として、中野区や町田市など、委託管理としては、品川区の中央公園・海上公園他と荒川区立宮前公園を行っています。
指定管理の実績はこちらから
業務委託管理の実績はこちらから
契約が違っても、利用者にとっては関係ありません。どのような契約体系であっても利用者から信頼される、総合的なパークマネージメントを当社は目指しています。
管理実績
指定管理者(構成企業)
Q.5指定管理者制度とPFI法の違いは何ですか?
A.5
法令の根拠が異なります。指定管理者制度は、地方自治法のもとに、PFIはPFI法のもとに定められた手法です。
指定管理者制度は、公園設置者である行政に代わって、公園施設の使用許可や公園施設内で行われる行為制限に係る許可を行うことのできる権限を有しています。指定管理者はこれらの権限の元、施設運営の一環で「自主事業」として地域住民の利用促進を目的にイベントや活動を企画・実施することが可能です。指定管理者制度は事業期間を5年以上としている施設もありますが、5年としている施設が多いです。
PFI事業は、民間が資金を調達して公共施設の整備をしたり、維持管理運営を一体的に実施する事ができます。
また、PFI事業では事業期間を最長30年まで延長する事ができます。
法令の根拠が異なります。指定管理者制度は、地方自治法のもとに、PFIはPFI法のもとに定められた手法です。
指定管理者制度は、公園設置者である行政に代わって、公園施設の使用許可や公園施設内で行われる行為制限に係る許可を行うことのできる権限を有しています。指定管理者はこれらの権限の元、施設運営の一環で「自主事業」として地域住民の利用促進を目的にイベントや活動を企画・実施することが可能です。指定管理者制度は事業期間を5年以上としている施設もありますが、5年としている施設が多いです。
PFI事業は、民間が資金を調達して公共施設の整備をしたり、維持管理運営を一体的に実施する事ができます。
また、PFI事業では事業期間を最長30年まで延長する事ができます。
PFIの実績はこちらから
スポーツ公園の管理運営業務について
ここでは、スポーツ公園の管理運営業務について、パークマネージメント事業部の山崎さんが働く中野区公園管理の仕事を通じて得た知見を教えてもらいます。
山崎さんが紹介するスポーツ施設の管理運営の仕事はこちら(採用記事)
Q.6公園の管理運営業務とは、どんなことをするもの?
A.6
定められた要求事項をもとに事業期間における提案書を作成します。プレゼンなどを経て事業者として選定された場合は、それをもとに単年度ごとに事業計画を作成します。
事業計画のもと、運営業務では、窓口業務、自主事業の計画立案と実施、野球連盟など利用団体との利用調整、ホームページ作成と更新、人材育成の教育訓練、事業報告書の作成等、多岐にわたります。
定められた要求事項をもとに事業期間における提案書を作成します。プレゼンなどを経て事業者として選定された場合は、それをもとに単年度ごとに事業計画を作成します。
事業計画のもと、運営業務では、窓口業務、自主事業の計画立案と実施、野球連盟など利用団体との利用調整、ホームページ作成と更新、人材育成の教育訓練、事業報告書の作成等、多岐にわたります。
維持管理では、運動施設の管理、公園全体の清掃、植物の管理、建物や設備の管理、修繕や安全対策の取り組みなど、こちらも多くの業務があります。
「業界研究・スポーツ施設管理運営の仕事」はこちらから
Q.7スポーツ公園では、どんなことがサービス向上につながりますか?
A.7
悪天候後の利用再開速度を向上させるための細目な整備や、定期的な巡視を心掛けています。
施設が空いている場合には、スポーツのみならず、多目的に利用できる場所として一般の利用者が活用できるよう整備をします。
常に安全なスポーツ施設として利用できることがサービス向上につながります。
悪天候後の利用再開速度を向上させるための細目な整備や、定期的な巡視を心掛けています。
施設が空いている場合には、スポーツのみならず、多目的に利用できる場所として一般の利用者が活用できるよう整備をします。
常に安全なスポーツ施設として利用できることがサービス向上につながります。

公園や公共スポーツ施設の施設・安全管理・環境保全について
Q.8公園の安全管理はどんなことに取り組んでいますか?
A.8
1日3回の巡回、毎朝礼時の危険予知活動(KY活動)、定期的なスタッフ研修、安全標語の掲示・KYシートの活用、四半期毎の安全点検の実施、遊具の日常点検・定期点検など。巡回では、不審者がいないか、危険物が落ちていないか、などは特に気をつけている点です。
1日3回の巡回、毎朝礼時の危険予知活動(KY活動)、定期的なスタッフ研修、安全標語の掲示・KYシートの活用、四半期毎の安全点検の実施、遊具の日常点検・定期点検など。巡回では、不審者がいないか、危険物が落ちていないか、などは特に気をつけている点です。

Q.9公園の環境保全はどんなことに取り組んでいますか?
A.9
植物管理で発生した剪定枝や、伐採した樹木は、クリスマスリース用のキットとしてイベントで販売したり、クラフト教室で活用しています。
その他、蛍光灯のLED化、落ち葉の堆肥化、空調を効率的に稼働して、外気を活用することなどに取り組んでいます。
植物管理で発生した剪定枝や、伐採した樹木は、クリスマスリース用のキットとしてイベントで販売したり、クラフト教室で活用しています。
その他、蛍光灯のLED化、落ち葉の堆肥化、空調を効率的に稼働して、外気を活用することなどに取り組んでいます。

販売したリースキッド
公園や公共スポーツ施設の地域連携について
Q.10地域連携として行っていることは?
A.10
地元の商店街連合会や区内で活動している団体との連携事業として、チャリティーコンサート・バザーなどを実施しています。
また、中野区図書館との連携事業として、図書館内の展示スペースへの広報物の展示を行っています。図書館の職員さんが紙芝居などを使って公園内の施設で読み聞かせを行うイベントも昨年初めて行いました。グローバルな取り組みとして、インドネシアのワヤンという影絵劇の上演は、大変人気で、多くのお客様に鑑賞いただきました。
また、さらに、区民・地域住民による自主的な意思により参加していただく活動の『パーククラブ』では、花壇のお手入れや、哲学堂公園の歴史を、共に学ぶ学習会を開催しました。
地元の商店街連合会や区内で活動している団体との連携事業として、チャリティーコンサート・バザーなどを実施しています。
また、中野区図書館との連携事業として、図書館内の展示スペースへの広報物の展示を行っています。図書館の職員さんが紙芝居などを使って公園内の施設で読み聞かせを行うイベントも昨年初めて行いました。グローバルな取り組みとして、インドネシアのワヤンという影絵劇の上演は、大変人気で、多くのお客様に鑑賞いただきました。
また、さらに、区民・地域住民による自主的な意思により参加していただく活動の『パーククラブ』では、花壇のお手入れや、哲学堂公園の歴史を、共に学ぶ学習会を開催しました。
毎年行っている、復興支援バザーでは大雨の年もありましたが、それでも80名近いの方が来場されました。こうした、地域の方々と連携してイベントを作り上げるというのも楽しみで、仕事のやりがいとなっています。


山崎 俊平 Shunpei Yamazaki
パークマネージメント事業部
スポーツの仕事紹介の関連記事


-e1739239751868.jpg)









